GDPの構成要素
今回はGDPの構成要素について説明していきます。
この文章を読むことで、GDPの恒等式と各構成要素について学ぶことができます。
GDPの恒等式
経済指標として最も重要なものの一つ、国内総生産(GDP)は4つの要素が積み重なって計算されています。
それを示すのが次の数式です。
Y(GDP)=C(消費)+I(投資)+G(政府支出)+NX(純輸出)
この式はいつでも正しくなります(恒等式)。
つまり、なんらかの支出があればこの4つの要素、すなわち消費、投資、政府支出、純輸出のいずれかに割り振られ、GDPに組み込まれます。
とある主婦がホットドッグを買った時、あるいは企業が工場を建設した時、また政府が道路をつくるとき、あるいはブラックタイガー(海老)をフィリピンから輸入するとき、すべてがこの式の中に含まれるのです。
では、具体的に各要素について見ていきましょう。
構成要素1:消費
消費は「家計による支出」と定義づけられます。
食品や書籍といった有形の消費はもちろん、エステや散髪といった無形のサービスにも適用されるほか、洗濯機や冷蔵庫、車やバイクといった耐久財に対してもこの要素が適用されます。
また、教育もこの消費に当てはまると言われます。
しかし、その性質から「教育費は投資だ」という声もあります。
対して、一見消費である新築住宅の購入に関しては消費ではなく、慣習的に投資に分類されることに注意しましょう。
構成要素2:投資
ではこの投資とはなんでしょうか。
「より多くの財・サービスの生産のために使われる財の購入」、それが投資です。
企業が行う設備投資や在庫、建物の購入などがこれにあたります。
注意したいのは「在庫」についての理解です。
これについては少し日常生活とは異なった理解が必要なので、例を挙げて説明しておきましょう。
【例題1】
酒造会社Aと取引のあるビン工場Bが品番Xのビンを30000本製造しました。
しかし、酒造会社Aは10000本しかXを発注しませんでした。
ビン工場Bは残りの20000本を自社の倉庫に在庫として保管し、次の発注に備えます。
<解説>
この時ビン工場Bは自社で製造した品番Xのビン20000本を「自ら購入した」とみなされます。
つまり、Bはいつか来る発注のために20000本分の投資支出を行ったのです。
そして、この在庫の中から5000本出荷すると、Bの在庫投資がマイナス5000本となり、それを購入した酒造会社Aの5000本への支出のプラスと相殺されます。
こうして「生産」に特化して経済を追うことで、GDPの数値を正確に測ろうとするわけです。
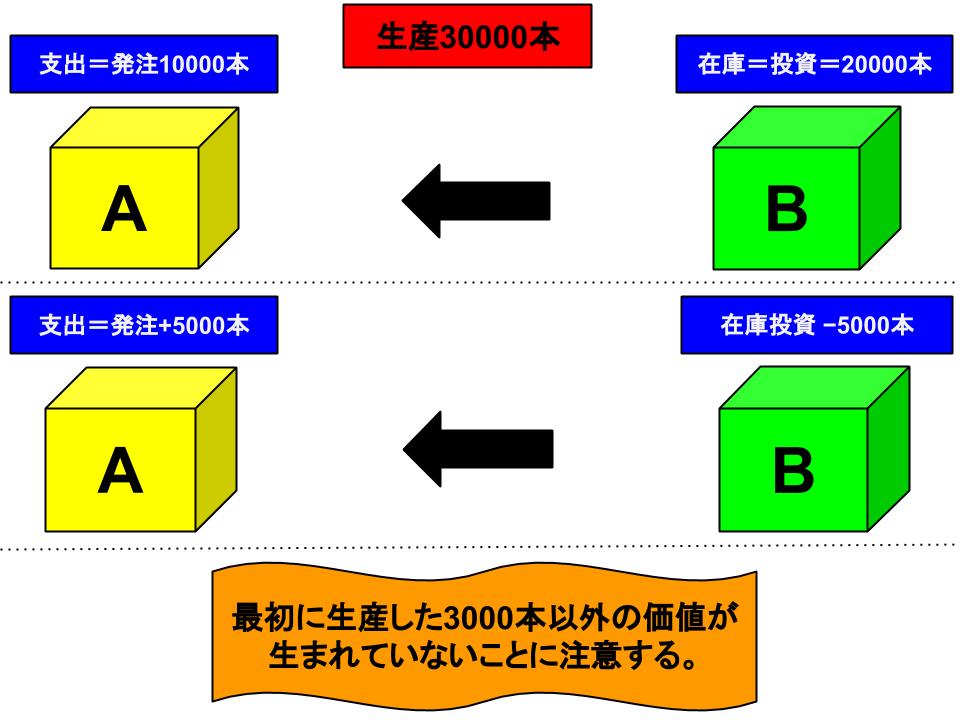
構成要素3:政府支出
政府支出は国、地方問わず自治体が行う財・サービスへの支出を指します。
「公務員への給与支払い」や「道路工事などの公共事業への支出」などがそれにあたります。
これだけなら文字通りの意味として理解できますが、ここでもう一つ「移転支出」という言葉について理解が必要です。
これは振替支出とも呼ばれ、財・サービスとの交換を伴わない支出を言います。
例えば、生活保護費や雇用保険などの支出、公務員の退職金などがこれに当てはまります。
なんらかの財やサービスを政府が得ないにもかかわらず、支出が行われている場合には、これを移転支出として計上するのです。
この移転支出は政府支出として扱われないので注意しましょう。
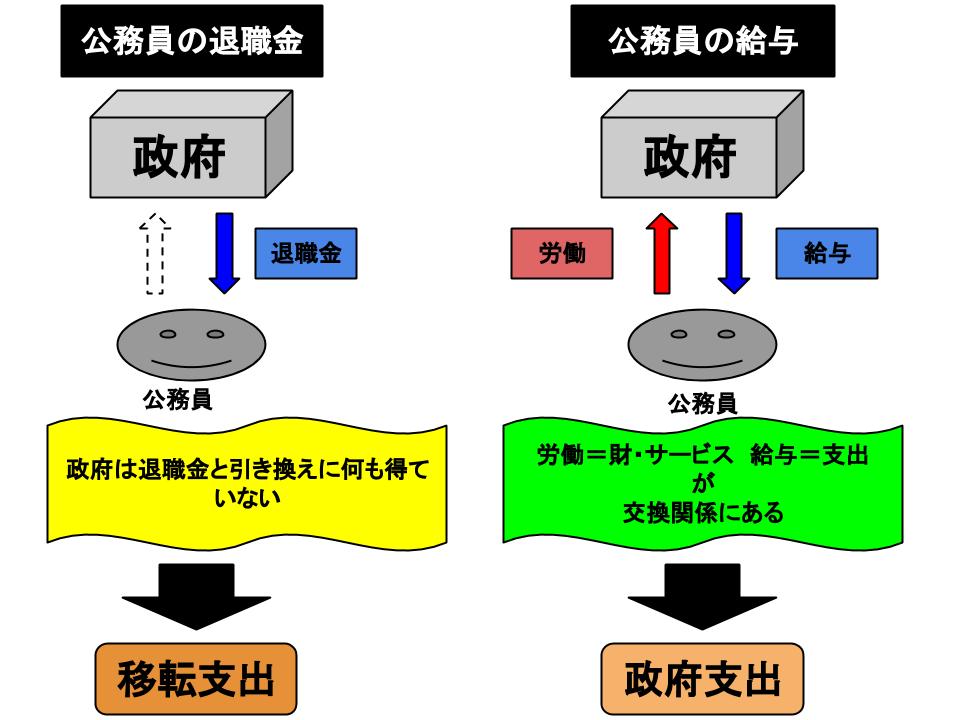
構成要素4:純輸出
純輸出は貿易収支ともいい、自国の財を他国が購入した額(輸出)から、他国の財を自国が購入した額(輸入)を差し引いたものを指します。
トヨタの自動車をアメリカが購入すれば、日本の純輸出額は増加します。
ところで、この「純」とはなんでしょうか。これは輸出から輸入を差し引く、という手続きを意味します。
つまり、貿易が赤字なのか、黒字なのかをすぐにわかるようにしてあるわけです。
しかし、ここで疑問が浮かびます。
「輸入をマイナスとして含んでしまうとGDPへの影響にはならないのか」というものです。
具体的な数字を挙げてこの問題を解決しておきましょう。
【例題2】
日本がアメリカから、とうもろこしを3万ドル輸入したとします。
対して、アメリカは日本から車を5万ドル輸入したとします。
これについて純輸出と、国内の支出の関係を考えてみましょう。
<解説>
とうもろこしを3万ドル輸入した場合、純輸出にはマイナス3万ドルが計上されます。
5万ドルの車を輸出すると、プラス5万ドルが純輸出に計上されます。
これだけですと、一見輸入によって純輸出が減少し、それに伴いGDPが減少しているように見えます(冒頭の式を思いだしましょう)。
しかし、この時同時に、国内ではとうもろこし3万ドルの支出が行われていることに着目しましょう。
つまり、国内の支出に関してプラス3万ドルが計上されます。
これにより相殺が起こり、結果としてGDPには影響が出ない仕組みになっています。
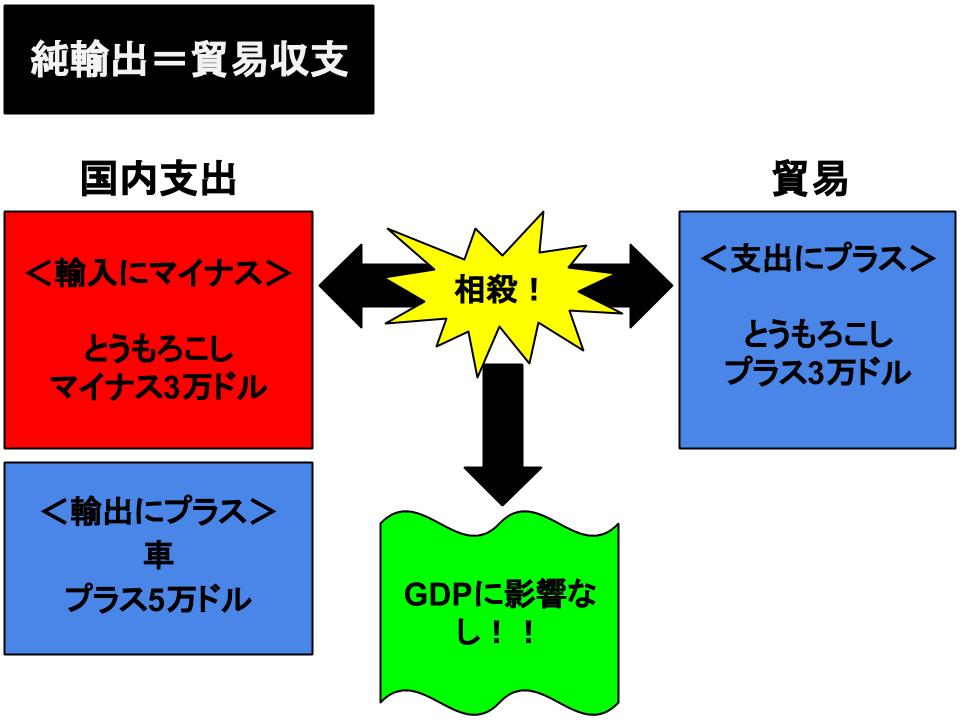
まとめ
Y(GDP)=C(消費)+I(投資)+G(政府支出)+NX(純輸出)
消費=家計による支出
投資=より多くの財・サービスの生産のために使われる財の購入
政府支出=自治体が行う財・サービスへの支出(移転支出は除く)
純輸出=貿易収支=輸出?輸入
関連ページ
- 経済学の十大原理
- 経済変動の重要な3事実
- 金融資源の国際的フロー
- 財の国際的フロー
- 国際的フローの貯蓄と投資の関係
- 日本は貿易すべきか
- 均衡変化の分析
- 財政赤字と財政黒字
- 中央銀行とは
- 古典派の二分法と貨幣の中立性
- 閉鎖経済と開放経済
- 会社の形態
- GDPの構成要素
- 消費者物価指数とは
- 消費者余剰
- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響
- 需要とは
- 経済モデル
- インフレ影響に対する経済変数補正
- 経済成長と公共政策
- 経済の所得と支出(マクロ経済学)
- 経済学の重要な恒等式
- 経済学とは
- 経済学者の意見が一致しない理由
- 効率と公平のトレードオフ
- 弾力性と税の帰着
- 弾力性とは
- 実証的分析と規範的分析
- ITを活用した経営戦略(コピー)
- 失業の測定方法
- 株式市場と債券市場
- 経済学の重要な恒等式
- 総需要曲線
- 短期の総供給曲線が右上がりの理由
- 均衡とは
- 市場均衡の評価
- 外部性に対する公共政策
- 外部性とは(厚生経済学)
- 金融仲介機関とは
- 金融システムとは
- 摩擦的失業と構造的失業
- GDPデフレーターとは
- GDPは経済厚生の尺度として妥当か
- GDP(国内総生産)とは
- GDPデフレーターと消費者物価指数
- 総需要曲線
- 投資インセンティブ
- 職探しと失業保険
- 貸付資金市場
- 市場と競争(ミクロ経済学)
- 市場の効率性
- 生計費測定の3つの問題
- 失業の測定方法
- ミクロ経済とマクロ経済
- 総需要と総供給のモデル
- 貨幣価値と物価水準
- 貨幣の流通速度と数量方程式
- 貨幣とは
- 貨幣市場の均衡
- 貨幣数量説と調整過程の概略
- 純輸出と純資本流出の均等
- 戦後の日本経済の歩み
- 価格規制(政府の政策)
- 価格と資源配分
- 生産者余剰
- 生産可能性と比較優位、および特化・交易
- 生産性とは
- 購買力平価(PPP)とは
- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)
- 実質GDPと名目GDP
- 実質利子率と名目利子率
- 景気後退と不況
- 貯蓄インセンティブ
- 貯蓄と投資
- 科学的な経済学
- 短期の経済変動
- 株式市場と債券市場
- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)
- 供給とは
- 税と公平性
- 税金とは
- 税と効率性
- 経済学の主要学説
- 短期の総供給曲線が右上がりの理由
- 短期の総供給曲線がシフトする理由
- 総供給曲線
- 失業とは
- グラフの用法
- 経済の波
- 世界各国の経済成長
